デジタルマーケティング戦略の中でも、メールマーケティングは特に高い費用対効果を実現できる施策として注目されています。しかし、多くの企業では「メールの開封率やクリック率は把握しているが、実際の商談や売上への貢献度が見えない」という課題を抱えているのではないでしょうか。
本記事では、メールマーケティングの費用対効果を算出して、マーケティング活動全体の意思決定につなげる実践的な方法について解説します。
- メールマーケティングにおける費用対効果の定義
- 【実務で使える】メールマーケティングにおける費用対効果の算出方法
- 複数施策の貢献度を正しく評価するマルチタッチアトリビューション分析の実装方法
- 【営業と連携】メールマーケティングの費用対効果を最大化する営業部署との連携項目4選
- 貴社は当てはまる?メールマーケティング施策に注力すべき2つの条件
- 【無料で試せる】メールマーケティングの費用対効果算出ツール
- 【テンプレ付き】メールマーケティングの費用対効果を社内に説明する手順
- 【よくある質問】メールマーケティングの費用対効果に関する疑問点や悩みに回答
- メールマーケティング施策の費用対効果を正しく評価して予算配分を決めましょう
当社はBtoB中小企業の商談化支援を中心とした、メールマーケティングやMA導入・運用、マーケティング戦略設計に強い会社です。
「商談数が増えない」「コンテンツ案が思いつかない」「どう改善すればいいか分からない」というお悩みがあればお気軽にご相談ください!無料の壁打ち相談も受付けております。
この記事を書いた人
合同会社クロスコムの代表|専門商社にて7年間のBtoB営業を経て、マーケティング業界に参入。中小企業を中心に100社以上のBtoBマーケティング戦略設計や施策実行を支援。MA構築・運用とコンテンツ企画制作による商談数拡大の支援が得意。
メールマーケティングにおける費用対効果の定義
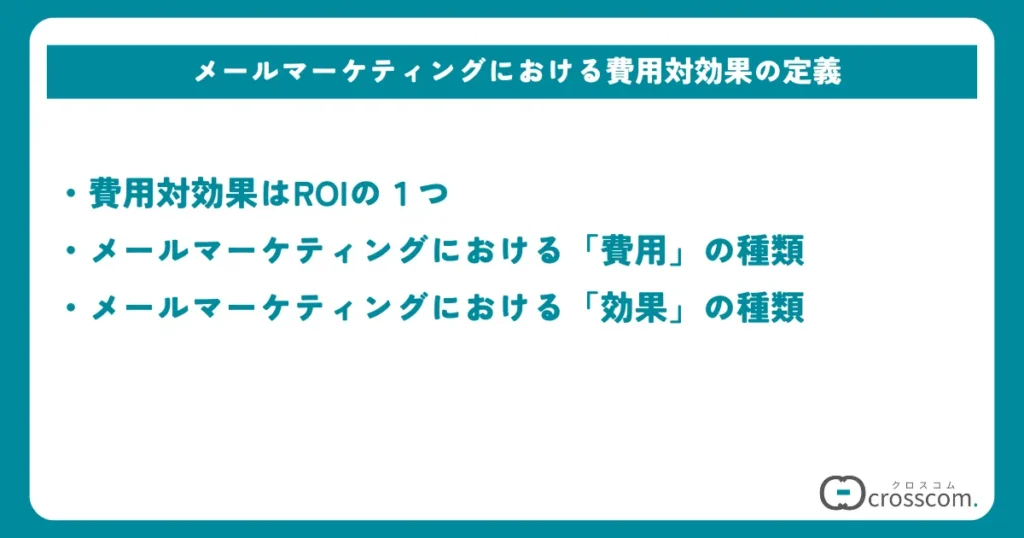
メールマーケティングの費用対効果を算出する前に、まず「費用対効果」という概念を正確に理解する必要があります。多くの企業では、開封率やクリック率といった指標に注目しがちですが、これらは最終的な事業成果との関連性が測定しづらい指標です。経営判断につながる費用対効果を適切に示すには、「費用と効果をどう定義するか?」をまず整理しておく必要があります。
ここでは、メールマーケティング施策における費用と効果の種類について解説していきます。
費用対効果はROIの1つ
費用対効果という言葉は、広告やマーケティングの現場で広く使われていますが、ROI(Return on Investment)の一部に含まれる概念を指しています。ROIとは「投資から得られたリターンをコストで割った比率」を意味し、金融投資や広告出稿など、幅広い分野で共通して使われています。
広告やキャンペーンで扱うROIは、基本的に以下の2つに大別されます。
①費用対効果・・・短期間で効果を発揮し、施策終了後に効果がなくなる「短期視点」のROI
②投資対効果・・・短期的な効果にあわせて、施策終了後も中長期にわたり効果が残る「中長期的視点」のROI
しかし、広告やキャンペーン活動の場合、ROIの対象となる「効果」と「費用」の範囲は状況によって異なります。それは、短期的な売上だけを見るのか、長期的なブランド形成効果を含めるのか、あるいは営業活動との相乗効果を評価するのかなど「目的次第」で解釈が変わってくるということです。
具体例でいうと、メール配信直後に発生した売上やリード獲得は「費用対効果」として捉えられ、一方で、定期的なニュースレターを通じてブランド認知が高まり、半年後に商談が成立するようなケースは「投資対効果」にあたります。「投資対効果」は、短期的な数値成果だけを追うのではなく、メールが顧客関係の強化や将来的な収益機会を生み出す点も、効果として含める必要があります。
このように、ROIといっても「費用対効果」と「投資対効果」は意味が異なるので、明確に理解しておくことが、分析を正しく行う上で重要です。今回の記事では、「費用対効果」を前提に算出方法を考えていきます。
メールマーケティングにおける「費用」の種類
次に、メールマーケティングにおける費用項目を考えていきます。すぐに思いつく費用として、メール配信ツールやマーケティングオートメーション(MA)ツールといったツール費用が挙げられますが、他にもいくつか考えられます。例えば、以下のとおりです。
- ツール費・・・使用ツールのライセンス料(初期費用・月額費用)
- 人件費・・・コンテンツ企画・コピーライティングの工数、デザイン・HTMLコーディング工数、営業部門のフォローアップ対応時間など
- 外注費・・・制作会社やマーケティング支援会社への委託費用、翻訳・デザイン・データ整備などスポットアウトソース費用
まず、費用の中心となるのはツール利用料です。初期導入費用や月額課金はもちろん、配信数やアカウント数に応じて料金体系が変わるツールがほとんどでしょう。
次に大きいのが人件費と外注費です。コンテンツ企画・デザイン・ライティング・効果測定などにかかる工数を正しく積算する必要があります。例えば、1年間のメール施策を実施する際に「配信ツール費用36万円」「人件費120万円」を合算して156万円とした場合、この数字が費用対効果の計算の分母となります。もし人件費を含めずに費用対効果を算出すると、費用対効果を過大評価する危険があります。
費用は単に「配信にかかったお金」ではなく、関連するツールや関わる社員の人件費、外注費も含めて考えましょう。
メールマーケティングにおける「効果」の種類
次に「効果」の項目です。効果指標の定義も、費用対効果の測定に大きく影響します。ここで重要なのは「目に見える成果を優先する」ことです。商談数や受注数、受注金額といった具体的な成果は定量的に評価できますが、ブランド想起率やプレファレンス向上といった定性的な効果は数値化が難しく、費用対効果の算出に組み込むのは適しません。
たとえば、メールマーケティング施策を導入したことで、資料請求が20件、そのうち商談に発展したのが5件、最終的に契約に至ったのが2件で売上が500万円だったとしましょう。この場合、商談数・受注数・受注金額が「効果」として算出可能です。さらに、商談ごとに成約確度を掛け合わせた見込み売上を算出すれば、より現実的な収益予測が立てられます。
一方で「ブランド認知が上がった」「読者からポジティブな反応を得られた」といった成果も重要ですが、これが費用対効果の計算対象とするのではなく、投資対効果として定性調査を通じて評価するのが望ましいと言えます。
このように、メールマーケティングの効果を「売上に直結する成果」と「副次的な効果」に切り分けてから、まずは前者に基づいて費用対効果を算出することが客観的な分析につながります。
【実務で使える】メールマーケティングにおける費用対効果の算出方法
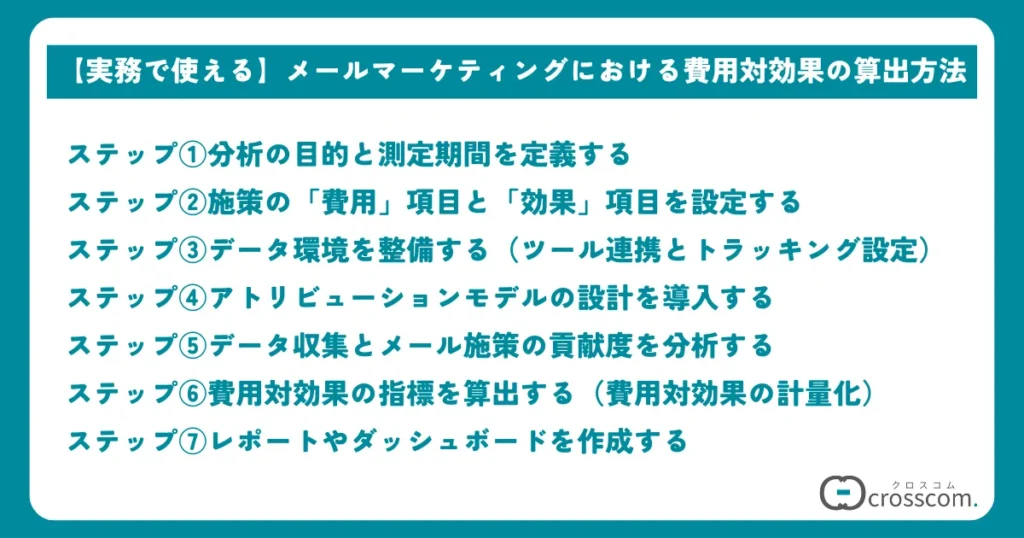
前章で「費用対効果」について整理したので、ここでは7つのステップに分けて、メールマーケティングにおける費用対効果を算出する実践的なプロセスを解説します。
具体的な実務イメージを持ってもらうために、今回はあるBtoB研修サービス企業が「法人向けIT研修サービス」をメールマーケティングで販売したケースも交えて、解説していきます。
ステップ①分析の目的と測定期間を定義する
費用対効果の算出で最初にすべきことは、目的と測定期間を明確に定義することです。これを行うことで、経営層に対して「どの投資がどれだけ成果につながったのか」を定量的に説明することができるため、経営判断の意思決定に役立ちます。
目的が曖昧なままでは、分析結果をどう活用するか分からなくなり、また測定期間が定義されていなければ、どこまでの費用と効果を算出対象とすべきか分からなくなります。特にBtoB領域ではリード獲得から受注まで数ヶ月以上かかることも多いので、測定期間を短く設定すると費用対効果が過小評価されてしまうでしょう。
例えば、BtoB研修サービスを運営する企業の経営層から「メールに人とお金をかけているけれど、実際に売上に貢献しているのか?」と問われたとします。BtoBの研修サービスは、問い合わせから契約まで平均3か月かかるため、1カ月単位で計測すると、メールで興味を持ったお客様がちょうど契約するタイミングを逃してしまい、正しい計測ができなくなってしまいます。
そこで、マーケティング部は、「2025年の第1四半期(Q1)のメールマーケティング施策が、どれだけ商談や受注につながったかを数値で示すことで、第2四半期(Q2)も施策を継続するか判断してもらう」と定義することで、経営層へ報告する取り付けを行いました。これが、目的と測定期間の正しい設定方法です。
このように、分析目的と期間を先に定義することで、「何のために費用対効果を算出するのか?」「その費用対効果は正しく評価できているのか?」に対する問いに回答でき、投資継続の判断材料として活用できるようになります。
ステップ②施策の「費用」項目と「効果」項目を設定する
次に必要なのは、施策の「費用」と「効果」を明確に設定することです。前章でもそれぞれ項目例を挙げましたが、これを行うことで、数字が単なる概算ではなく、経営判断の根拠を持った指標になるのでとても重要です。逆に、もし費用や効果の定義をあいまいにすると、投資対効果を過大にも過小にも評価してしまい、施策の継続可否や予算配分を誤るリスクがあります。
本来、費用対効果の定義は「費用に対して得られた利益の割合」であり、以下の計算式で求められます。
費用対効果 = (売上 ー 費用) ÷ 費用 × 100例えば研修サービス企業では、費用項目を「メール配信ツール利用料」「コンテンツ制作費」「担当者の作業時間」に、効果項目を「メール施策による商談数」「受注数」に絞りました。前章でお伝えした通り、開封率やクリック率といった効果項目は、売上や利益へ直結しないため、効果項目から外すのは有効でしょう。また、もし費用に人件費を含めなかった場合、費用対効果は過大に評価れてしまい、経営層に誤解を与える可能性が出てしまいます。
ステップ③データ環境を整備する(ツール連携とトラッキング設定)
次に欠かせないのが、費用と効果を正しく集計する「データ環境の整備」です。これを行うことで、「メールマーケティング施策がどんな成果を生んだのか」を正確に追跡できるようになります。
データがバラバラのままでは、どの施策が本当に成果を出しているのかが見えません。特に複数のツールを使っている場合、それぞれの数字が噛み合わず、費用対効果の算出が机上の空論になってしまいます。
たとえば、このBtoB研修サービス企業では、メール本文に設置したURLには必ずUTMパラメータを付与し、Google Analytics 4(GA4)上でWebサイトのアクセス流入元を確認する際に、参照元名で「メール」と識別できるように設定を行いました。また、HubSpotでは、WebサイトにトラッキングIDを埋め込むことで、個々のコンタクトごとにメールに接触してWeb問い合わせに至ったかを確認しています。
このように、GA4やMA・CRMツールの導入、連携することで、費用対効果を可視化するデータ環境が整備できます。
ステップ④アトリビューションモデルの設計を導入する
データが揃ったら、次は「どの施策がどれだけ成果に貢献したか」を評価する仕組み、つまりアトリビューションモデルを設計します。一般的には、GA4でデフォルト設定されている「データドリブンアトリビューション」を導入することで、メールマーケティング施策の貢献度合いを、AIによる機械学習を用いて正しく測ることができます。
そもそも、なぜデータドリブンアトリビューションを選ぶべきかという話ですが、顧客は1回のメールでいきなり契約するのではなく、広告・セミナー・営業電話など複数のタッチポイントを経てようやく購買意欲が高まり購入に至るからです。特にBtoBにおいては購買プロセスが複雑すぎるため、最後にクリックしたチャネルだけを成果にするのは実態と乖離して評価してしまう可能性があります。
たとえば、このBtoB研修サービス企業は、GA4の「データドリブンアトリビューション(DDA)」を採用し、過去の行動データをAIに学習させ、各接点の寄与度を自動で割り振ける施策を行っています。「メールで成功事例を読んだことがきっかけで、後にセミナー参加と契約に至った」ことがWeb行動上で確認できれば、メールにも一定の貢献が配分されます。
従来なら「セミナーだけの成果」とされていたものが、データドリブンアトリビューションにより「メールがセミナー参加のきっかけとなった」と実態により近い状態で証明できるようになったというわけです。
このように、データドリブンアトリビューションのモデル設計を導入することで、メールが「最初のきっかけ」「途中の育成」「最後の後押し」のどこで効いているのかを明確にできます。
ステップ⑤データ収集とメール施策の貢献度を分析する
アトリビューションモデルを設計したら、次は実際にデータを収集して「どのメール施策が成果に寄与したのか」を定量的に分析していきます。
具体的には、メール配信時に付与したキャンペーンIDやUTMパラメータをもとに、どのメール経由で訪問・コンバージョンしたかを追跡する分析を行います。また、フォーム送信やイベント参加など重要なコンバージョンはGA4でカスタムイベントを設定し、「メールA経由で来訪→フォーム送信→営業フォロー→受注」という一連の流れをデータ上で再現できるようにします。
HubSpotなどのマーケティングオートメーション(MA)ツールを使っている場合、メールの開封・クリック履歴からスコアリングを行い、一定スコアで営業に引き渡すといった運用で貢献度を可視化する企業もあります。見込み客の行動データ収集とスコアリングを徹底し、「スコアが一定以上=購買意欲が高まった」と判断したリードだけ営業がアプローチするルールを策定することで、無駄な追客を減らし営業リソースを効率化できます。
実際に、GA4の「アトリビューションパス」(コンバージョン経路)レポートでは、複数のタッチポイントにまたがるユーザーのコンバージョン経路と各チャネルの貢献度を視覚的に確認できます。データドリブンアトリビューションにより、メールや検索流入、直接流入などがそれぞれコンバージョンにどの程度寄与したかが、AIによる機械学習で自動的に割り振られるので非常に便利です。
このような分析から「どのメールキャンペーンが商談創出に効いているか」「営業前の接触チャネルは何か」などを把握でき、各施策の役割分担をデータで証明できるようになります。効果の高いチャネルに予算を厚く配分したり、逆に費用対効果の低い施策を改善・中止する判断につなげることが可能になります。
ステップ⑥費用対効果の指標を算出する(費用対効果の計量化)
ここまでの準備と分析を経て、ようやく費用対効果を算出できる状態になります。経営層に「投資した費用がどれだけ回収できたか」をシンプルに説明することで、今後のメールマーケティング施策における継続有無と予算配分について意思決定をしてもらえるようになります。
たとえば、BtoB研修サービスの当初の目的は「2025年の第1四半期(Q1)のメール施策が、どれだけ商談や受注につながったかを数値で示す」でしたが、この四半期の数値を計測した結果は以下の通りでした。
商談数:10件
受注数:3件
売上:600万円
費用:59万円この場合、費用対効果は(600−59)÷59=918%の結果になります。また、商談単価は59万円÷10件=5.9万円、受注単価は59万円÷3件=19.6万円。売上費用比は600万円÷59万円=約10倍という結果でした。つまり「1件の商談獲得に6万円弱、1件の契約獲得に20万円弱がかかり、投資1に対して売上10を生んだ」と数字で示すことができました。
こうした具体的な数値をもって経営層に説明することで、「メールマーケティングは費用対効果の高い施策である」と納得感を持ってもらい意思決定してもらえるでしょう。
ステップ⑦レポート・ダッシュボードを作成する
最後に、算出した費用対効果を分かりやすく伝える作業です。これはExcelやスプレッドシートのような表計算ソフトをつかった簡易的なレポートでも構いません。ダッシュボードで作成するとより伝わりやすくなるので、レポート作成に余裕があれば使ってみるのもおすすめです。
たとえば、このBtoB研修サービス企業ではLooker Studioを使い、「月ごとの商談数・受注数推移」「商談までのアトリビューションパス」「施策ごとの貢献度」をダッシュボード化しました。さらにExcelに詳細な算出表を残し、「どのように数字を計算したか」を透明にしました。こうして経営層への報告会では、「メール施策は費用比10%で全体売上の20%を生んだ」と報告することができ、、経営層は一目でメールマーケティング施策の費用対効果を理解してもらい、次の四半期の予算増加を承認してもらいました。
このように、レポートとダッシュボードを通じて費用対効果を可視化することで、正しく経営判断ができるようになるわけです。以上が、メールマーケティングの費用対効果を算出する7ステップでした。
複数施策の貢献度を正しく評価するマルチタッチアトリビューション分析の実装方法
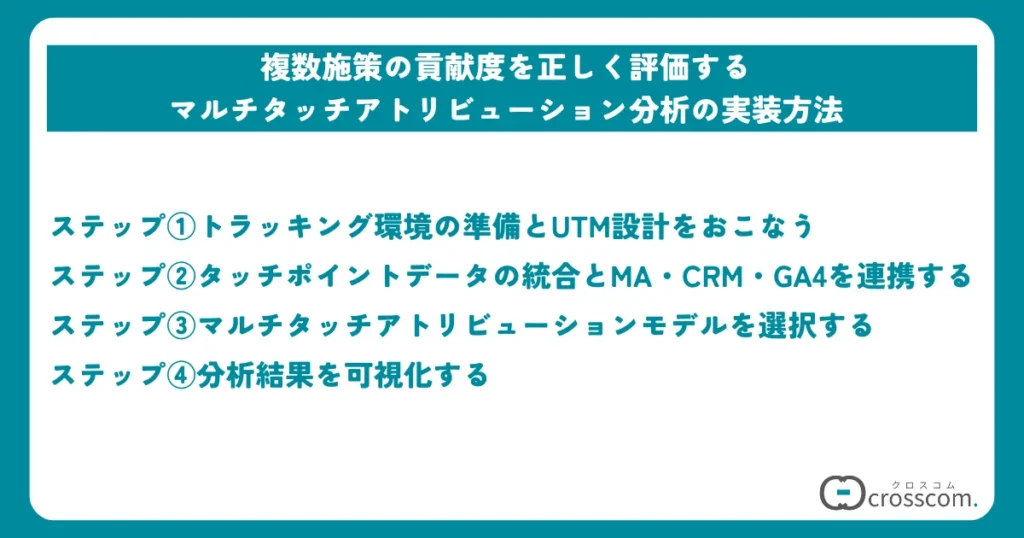
メールマーケティング施策の費用対効果を算出するプロセスを7ステップで紹介しましたが、現代のBtoBマーケティングでは、顧客が購買に至るまでに「複数のタッチポイントを経由」することが一般的です。メール、ウェブサイト、広告、営業電話、展示会など多様な接点をもって最終的な成約につながるため、単一チャネルの効果だけを見ていては正しく貢献度を把握できません。
しかし、マルチタッチアトリビューション分析を実装することで、各施策の相互作用や補完関係を定量化し、より精緻な費用対効果の評価が可能になります。ここでは実務で活用できる、マルチアトリビューション分析の具体的な実装方法を詳しく解説します。
ステップ①トラッキング環境の準備とUTM設計をおこなう
まず、マーケティング施策ごとのタッチポイントを漏れなく計測できる体制を整えます。具体的には、WebサイトにはGA4のタグを実装し、また、自社サイトにHubSpotのトラッキングコードを埋め込むことで、フォーム送信やメールクリックなどの顧客行動をHubSpot側でも記録できるようにします。
あわせて、メール本文内に設置するURLには、utm_source・utm_medium・utm_campaignなどのUTMパラメータを付与しましょう。UTMを統一した命名で設計し、CRMやGA4で紐付けておくことで、GA4の流入元データ(utm_medium=email等)に反映されるので、メールのCTAクリックやWebページ上の資料ダウンロードなども、一貫してイベントとして記録・分析できるようになります。
ステップ②タッチポイントデータの統合とMA・CRM・GA4を連携する
次に、収集したデータを一元的に統合し、コンバージョンまでの顧客ジャーニーを再現できるようにします。鍵となるのは、異なるツール間で同一のリードを対応付けるための共通IDの設計です。
具体的には、フォーム送信時に一意のトランザクションID(問い合わせIDなど)を発行し、GA4のコンバージョンイベントとHubSpot上のコンタクトプロパティの両方にそのIDを渡します。または、GTMを用いてフォームページでランダムなIDを生成しCookieに保持、送信完了時にそのIDをGA4のイベントパラメータとHubSpotの非表示フィールドに送信するといった方法もあります。
この設定により、GA4の流入経路データ(どのチャネルから来訪しコンバージョンしたか)とHubSpot・CRMの商談データ(そのリードが後にアポイントや成約に至ったか)を後段で紐づけることが可能になります。加えて、HubSpotのコンタクトIDやメールアドレスなども統合時に保持しておくと、ユニークなリード数の把握や重複除外に役立ちます。
ステップ③マルチタッチアトリビューションモデルを選択する
データ基盤が整ったら、どのアトリビューションモデルで効果を評価するかを決定します。モデルにより施策貢献度の配分が異なるため、マーケティング上の目的に合致したものを選ぶことが重要です。
代表的なモデルには以下のようなものがあります。
①線形(リニア)モデル・・・コンバージョンに至るすべてのタッチポイントに均等に貢献度を割り当てる
②時間減衰(タイムディケイ)モデル・・・すべての接点に貢献度を割り当てつつも、時間的にコンバージョン直前の接点に貢献度の高い重みをおいていく
③U字(U型)モデル・・・最初の接点とコンバージョン直前の接点に大きな貢献度(例:各40%)を割り当て、残りを中間接点に均等配分する
④データドリブンアトリビューションモデル・・・過去の蓄積データを基にして、コンバージョンに至るまでの接点ごとに自動的に貢献度を割り当てる
線形(リニア)モデルは、コンバージョンに至るすべてのタッチポイントに均等に貢献度を割り当てます。長期間にわたって複数チャネルでナーチャリングを行うBtoB商談プロセスでは、全施策の影響をバランスよく評価したい場合に適しています。ただし全てが等分になるため、特に効果の大きかった施策を単独で判断しにくいという注意点があります。
時間減衰(タイムディケイ)モデルは、すべての接点に貢献度を割り当てつつも、時間的にコンバージョン直前の接点に高い重みを置くモデルです。検討期間が長いものの最終的な後押し施策を重視したい場合に有効で、直近のキャンペーンや営業タッチの影響度を測定するのに適しています。
U字(U型)モデルは、最初の接点とコンバージョン直前の接点に大きな貢献度(例:各40%)を割り当て、残りを中間接点に均等配分するモデルです。BtoBマーケティングでよくある「初回接点(例:広告経由のサイト訪問や資料ダウンロード)」と「最終接点(例:営業との商談)」を特に重視しつつ、中間のナーチャリング施策も一定評価したい場合に適しています。
そして今回ご紹介したデータドリブンアトリビューションモデルは、過去の蓄積データを基にして、コンバージョンに至るまでの接点ごとに自動的に貢献度を割り当てるモデルです。購買に至るまで多様な接点を持ちつつ、顧客が購買プロセスのステージ間を行ったり来たりする複雑な購買行動を手軽に評価したい際に適しています。
小規模BtoBでは、まずデータドリブンアトリビューションモデルから検討するのが手間もかからないため、おすすめです。「成約直結の施策を知りたい」場合はラストクリックやJ型、「全般的な貢献度を公平に見たい」場合はリニアなど、目的に応じて使い分けましょう。
ステップ④分析結果を可視化する
最後に、得られたマルチタッチアトリビューション分析の結果を分かりやすく可視化し、施策改善に活かす運用を行います。HubSpotを利用の場合は、Marketing Hub Professionalを導入しているとアトリビューションレポート機能でコンタクト獲得や売上へのチャネル貢献度をグラフ化できます。
一方、GA4とCRMからデータをエクスポートしてBIツールでダッシュボード化する方法も有効です。広告のクリックやコストデータ(GA4)と、リードのアポイント数・商談化・成約データ(CRM・HubSpot)をGoogle BigQueryに集約し、Looker Studioでレポートを作成する手法があります。
こうした統合レポートにより、オンライン広告のリード獲得数だけでなく「その後何件商談・何件成約したか」まで含めたROIをチャネル別に評価できます。季節性やキャンペーン効果を加味した分析により、年間を通じた最適な予算配分計画を策定することも、重要な活用方法といえるでしょう。
【営業と連携】メールマーケティングの費用対効果を最大化する営業部署との連携項目4選
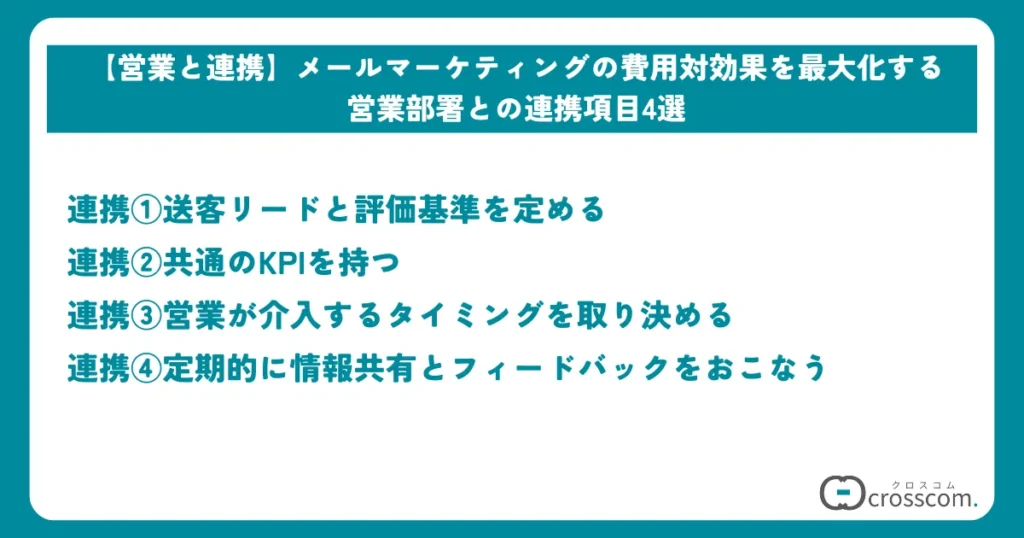
ここまで費用対効果の算出方法やツール設定に関する解説でしたが、メールマーケティングの成果は、営業部署と連携してはじめて商談・受注に至ります。どれだけ質の高いリードを獲得しても、営業との連携が不十分であれば機会損失に終わってしまうわけです。
では、メールマーケティング施策を実施するうえで営業部署とどのような連携を行うべきでしょうか。ここでは特に重要な4つの観点を取り上げ、実務に役立つ考え方を整理します。
連携①送客リードと評価基準を定める
1つ目は「送客リードと評価基準を定める」です。営業とマーケティングが共通のリード定義を持つことは、費用対効果を高めるうえで欠かせません。なぜなら、評価基準がずれていると「マーケは質が高いと考えるが営業は見込み薄と判断する」といった不一致が発生し、せっかくのリードが放置されるからです。
例えば、ある研修サービス企業では、業種や従業員規模、役職などの属性に加え、メルマガ経由のホワイトペーパーダウンロード数やWeb訪問回数といった行動を対象としたスコアリングモデルを、MAツールを使って設計しています。これにより「製造業・従業員100名以上・決裁権者・製品ページ3回以上閲覧・ホワイトペーパーダウンロード履歴あり」といった条件を満たすリードは、営業が優先的にアプローチすべき対象として客観的にすり合わせができます。
このように評価基準を明確にすれば、リードの質をめぐる議論が減り、営業もターゲット企業が定まりやすくなります。
連携②共通のKPIを持つ
2つ目は「共通のKPIを持つ」です。目標部門ごとに追いかける指標数値が異なると、連携が形だけに終わる可能性があります。したがって、両部門で共通のKPIを設定し、同じゴールに向かって協力する仕組みが費用対効果の向上には必要です。
たとえば、とある企業では従来、マーケティングはリード数やコンバージョン率を重視し、営業は商談数や受注率に注目する傾向がありました。しかし「メール経由で発生した商談数」や「メール起因の受注金額」といった指標を共通KPIにしたことで、マーケティングも営業も「費用対効果をどう高めるか?」という同じ視点をもって議論できるようになりました。
このようにKPIを一元化することで、マーケティング部署と営業部署の分断リスクをおさえ、双方の努力を成果につなげられるようになります。
連携③営業が介入するタイミングを取り決める
3つ目は「営業が介入するタイミングを取り決める」です。具体的には、「リードスコアが一定値を超えたら営業へ引き継ぐ」「資料請求やデモ依頼など明確な購入シグナル発生時に直ちに営業連絡する」等、どのタイミングで営業部署に介入してほしいか取り決めることです。
たとえば、とある企業では、マーケティング部署が獲得したリードを迅速に営業へ送客する仕組みとして、「フォーム問い合わせから1時間以内に営業が連絡する」など、受け渡し時のルールを明文化しています。問い合わせから1時間以内にコンタクトした場合、商談に進展する可能性が高くなる調査データもあることから、実際にこの迅速な営業介入は費用対効果の向上に極めて効果的です。
もし営業介入のタイミングが遅れると商談機会を逃す恐れがあり、リードへの初回フォローが遅れるごとに成約率が低下するリスクが高まるでしょう。
連携④定期的に情報共有とフィードバックをおこなう
4つ目は「定期的に情報共有とフィードバックをおこなう」です。週次・月次の定例ミーティングを開催し、メール施策で獲得したリードの質・進捗状況を確認しつつ、営業からのフィードバックをもとに議論する機会を設けることが重要です。
双方が閲覧できる共有ダッシュボードを用意し、リード数だけでなくパイプライン転換率や売上貢献額など共通KPIをトラッキングするのも有効でしょう。
より客観的に制度の高い情報共有を行う場合、マーケ施策から創出されたリードが最終的にどれだけ売上につながったかをCRM上で可視化(ファネル管理)し、マーケ部署と営業部署が合同で分析することもおすすめです。実際に営業とマーケ部署が統一のKPI目標(例:四半期でSQL25%増やす等)を持ち進捗を一緒に追うチームは、そうでない場合に比べ目標達成率が大幅に高まることが期待できるでしょう。
ほかにも、「顧客からよく聞かれる質問をFAQ形式のメールコンテンツにする」「営業が使っている効果的なセールストークをメールの件名に活用する」といった営業現場の声をコンテンツに反映することで、より見込み客の課題に刺さるメール施策としてブラッシュアップできるのでお勧めです。
貴社は当てはまる?メールマーケティング施策に注力すべき2つの条件

マーケティング部署と営業部署との連携で費用対効果を高める打ち手を整理してきましたが、そもそも「貴社はメールマーケティング施策に“投資すべき状況なのか”」について考える必要があります。
ここでは、メールマーケティング施策に注力すべき2つの視点をご紹介します。
条件①マーケティング予算が少額
1つめは「マーケティング予算が少額」の場合です。メールマーケティングは比較的低コストで高い費用対効果を実現できるため、リソースが限られた企業(スタートアップや中小企業など)でも、期待以上の成果を上げることができます。特にメルマガはブランド(特に中小企業)が巨額のマーケティング予算をかけずにブランド想起と関係構築が実現できる有効な手法の1つです。
たとえば、関心の高い見込み客リストへ継続的にメールを配信すると、ほとんど予算をかけずにかつ能動的にコンテンツを届けられるので、高額な広告よりも高い収益が得られることが十分に期待できます。Google広告やFacebook広告では1クリックあたり数百円から数千円のコストがかかる業界でも、既存の見込み客リストへのメール配信なら1通あたり数円から数十円程度で済むからです。
特にマーケティング予算が月額50万円以下の企業では、メール施策を軸とした戦略が効果的です。初期はメール配信ツールの月額費用(月1万円~3万円程度)と制作・運用の人件費のみで開始でき、成果に応じて段階的に投資を拡大できるメリットがあります。広告予算の変動に左右されない安定したマーケティングチャネルとして機能するでしょう。
条件②販売サイクルが長期間
2つ目は「販売サイクルが長期間」の場合です。意思決定プロセスに時間がかかるBtoB企業も、商談化までの見込み客との接点構築のためにメールマーケティング施策へ投資すべきです。BtoBバイヤーはメールによるコミュニケーションを最も好むため、ステップメールと定期的なメルマガ配信は、一貫性かつ関連性の高いコンテンツを通じて継続的に接点をつくれるので、見込み客との関係構築に有効です。
例えば、企業向けソフトウェアやコンサルティングサービス、設備投資を伴う商材などでは、初回接触から契約まで平均6ヶ月以上かかることが珍しくありません。この期間中、継続的にメールで有益な情報を提供することで、競合他社に比べて優位なポジションを維持できます。単発の広告では長期間の関係性構築は困難であり、メールの継続的なナーチャリング効果が特に威力を発揮します。
【無料で試せる】メールマーケティングの費用対効果算出ツール
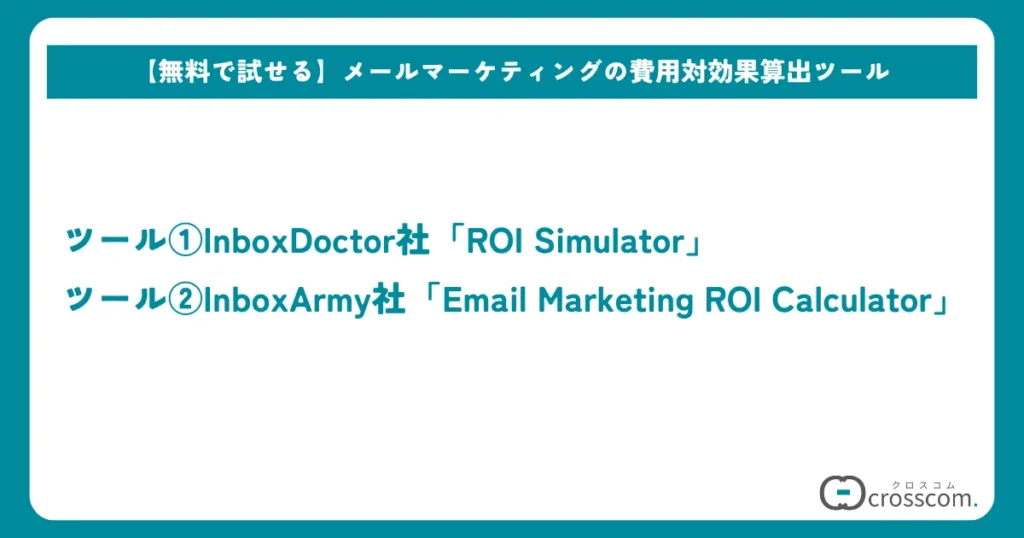
メールマーケティングの費用対効果の基礎検証ですが、無料ツールでも十分に始められます。実際に海外のメール配信プラットフォーム企業は、メールキャンペーンに関する費用対効果を算出するツールを無料で公開しています。
ここではメールキャンペーンの費用対効果を算出する代表的な2つをご紹介します。
ツール①InboxDoctor社「ROI Simulator」
InboxDoctor社が提供する「ROI Simulator」は、メールマーケティングキャンペーンの費用対効果を簡単にシミュレーションできる無料ツールです。このツールでは、メール配信数、開封率、クリック率、コンバージョン率、平均注文額などの基本的なパラメータを入力することで、期待される費用対効果を自動計算してくれます。
初心者でも直感的に操作でき、複雑な計算式を覚える必要がないため、メールマーケティング担当者が経営層への報告資料を作成する際の基礎データ収集にも適しているでしょう。
ツール②InboxArmy社「Email Marketing ROI Calculator」
InboxArmy社の「Email Marketing ROI Calculator」は、より詳細な費用構造を考慮したROI計算が可能なツールです。メール配信にかかる直接費用だけでなく、人件費やツール利用料、コンテンツ制作費なども含めて総合的にコスト計算できます。
入力項目が詳細であるため初期設定に若干の時間を要しますが、一度設定すれば継続的にデータを更新して精緻な分析を行えるメリットがあります。特に複数のメールキャンペーンを並行実施している企業にとって、優先順位付けや予算配分の判断材料として有用なツールといえるでしょう。
【テンプレ付き】メールマーケティングの費用対効果を社内に説明する手順
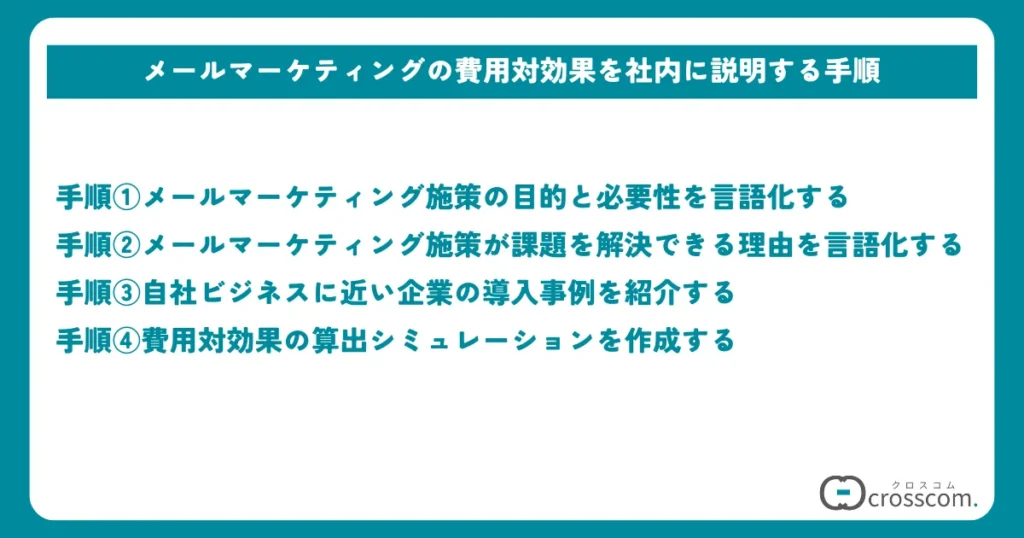
メールマーケティングのROIを正確に算出できても、それを社内の関係者、特に経営層へ意図通りに意思決定してもらわなければ、予算承認やマーケティング活動の戦略変更にはつながりません。
ここでは、算出した費用対効果を説得力のある形で社内に説明するための具体的な手順とテンプレートを提供します。
手順①メールマーケティング施策の目的とゴールを言語化する
まず、なぜメールマーケティングに取り組む必要があるのかを明確に説明する必要があります。単に「メールマーケティングをやりたい」ではなく、現在の事業課題とメール施策の関連性を論理的に整理することが重要です。
たとえば、目的の設定では、「新規顧客獲得の強化」「既存顧客のリテンション向上」「営業リードの質向上」などが挙げられます。目標といては「四半期で新規商談を20件創出し、そのうち5件の受注を目指す」といった定量的な表現を用いて説明すると有効でしょう。
- 新規顧客獲得数を増やすため
- 既存顧客のリピート率を上げるため
- 営業リードの質を上げるため
ゴール設定では、メール施策により期待される改善効果を明示します。「商談獲得単価を15万円→10万円まで削減」「月間新規商談数を10件→25件に拡大」「営業1人あたり月間商談数を5件→8件に増加」など、現状との比較で分かりやすく示すと、導入効果が分かりやすく伝わります。
- 商談獲得単価を15万円→10万円まで削減
- 月間新規商談数を10件→25件に拡大
- 営業1人あたり月間商談数を5件→8件に増加
手順②メールマーケティング施策が課題を解決できる理由を言語化する
次に、なぜメール施策が特定した課題の解決に適しているかを理論的に説明します。根本的な原因やビジネス特性を踏まえて論理的に説明することで、施策の妥当性を示します。
例えば、商談獲得単価の高騰が課題である場合、以下のような解決できる理由を説明するのがいいでしょう。「広告費の上昇により1件あたりのリード獲得コストが年々増加しているに比例し、商談獲得単価も高騰しています。BtoBビジネスでは購買検討期間が長いため、本格的に購買検討するタイミングで自社を想起してもらうことが重要です。
したがって、メールマーケティング施策を通じて休眠顧客へ低単価でかつ定期的に情報提供することで自社を記憶してもらい、購買検討開始するタイミング時に問い合わせしてもらうよう狙います。」といった説明を行います。
広告費の上昇により1件あたりのリード獲得コストが年々増加しているに比例し、商談獲得単価も高騰しています。BtoBビジネスでは購買検討期間が長いため、本格的に購買検討するタイミングで自社を想起してもらうことが重要です。
したがって、メールマーケティング施策を通じて休眠顧客へ低単価でかつ定期的に情報提供することで自社を記憶してもらい、購買検討開始するタイミング時に問い合わせしてもらう仕組みを作る点で、メールマーケティング施策は有効だと考えます。
また、自社の保有リソースとの適合性も説明に加えます。「社内にコンテンツ制作のノウハウがあり、外部委託コストを抑えながら質の高いメールコンテンツを継続的に提供できる体制がある」「既存顧客との関係性が良好であり、紹介や口コミによる新規リスト獲得の基盤がある」といった強みを活かせることも説明できるといいでしょう。
手順③自社ビジネスに近い企業の導入事例を紹介する
理論的な説明だけでなく、実際に自社の実態に近い企業でメールマーケティングが成功している事例を紹介することで、説得力が高まります。業界特性や課題背景が近い事例ほど、経営層の納得を得やすくなるのでおすすめです。
たとえば事例紹介では、主に以下のポイントで参考にするのがいいでしょう。
- 所有しているリソースは近いか?
- 課題背景は似ているか?
- ビジネス特性は似ているか?
- 実施した施策内容は?
- 得られた成果は?
ただし、他社事例の選定では、そもそもビジネス環境や取り組み時期だけでなく、企業のターゲット・サービス価値なども異なるため、必ず成功できるとは限りません。あくまで参考程度に、公開されている情報や実績のある企業の事例を使用するといいでしょう。また、自社との違いも正直に説明し、「A社とは業界が異なるが、BtoB向けの長期販売サイクルという点では共通している」といった注釈を加えることで、より客観性を保てます。
手順④費用対効果の算出シミュレーションを作成する
前述の算出方法に基づき、自社でメール施策を実施した場合の具体的な費用対効果のシミュレーション表を作成します。経営層が最も関心を持つ部分であるため、保守的で現実的な数値設定がいいでしょう。
ここで重要なのは、不確実性の高いマーケティング施策において、単一のシミュレーションだけでなく、悲観・普通・楽観の3シナリオを用意することです。
■悲観シナリオ(普通シナリオの達成度70~80%)
商談獲得単価や受注数など、効果指標を普通シナリオ数値の70~80%に設定し、競合の影響や市場環境の悪化も考慮します。「商談獲得単価200,000円、受注率10%の場合、年間ROI=80%」といった具合に、最低ラインでも一定の成果が期待できることを示します。
■普通シナリオ(想定通り)
業界標準値や類似企業の実績を参考に、現実的な数値を設定します。「商談獲得単価150,000円、受注率15%の場合、年間ROI=100%」のように、最も可能性の高いケースとして設定することで、予算承認の判断基準とします。
■楽観シナリオ(普通シナリオの達成度120~130%)
施策が順調に進んだ場合の上振れ効果を示します。「商談獲得単価120,000円、受注率20%の場合、年間ROI=120%」のように過度に楽観的な数値は避けつつ、実現可能性のある範囲での最大効果を示すといいでしょう。
3つのシナリオを比較することで、係争はリスクとリターンのバランスを判断しやすくなり、意思決定がしやすくなるでしょう。費用対効果の算出テンプレートは、個人情報なしで以下よりすぐにダウンロードできます。ぜひ経営層への説明にご活用ください。
【よくある質問】メールマーケティングの費用対効果に関する疑問点や悩みに回答
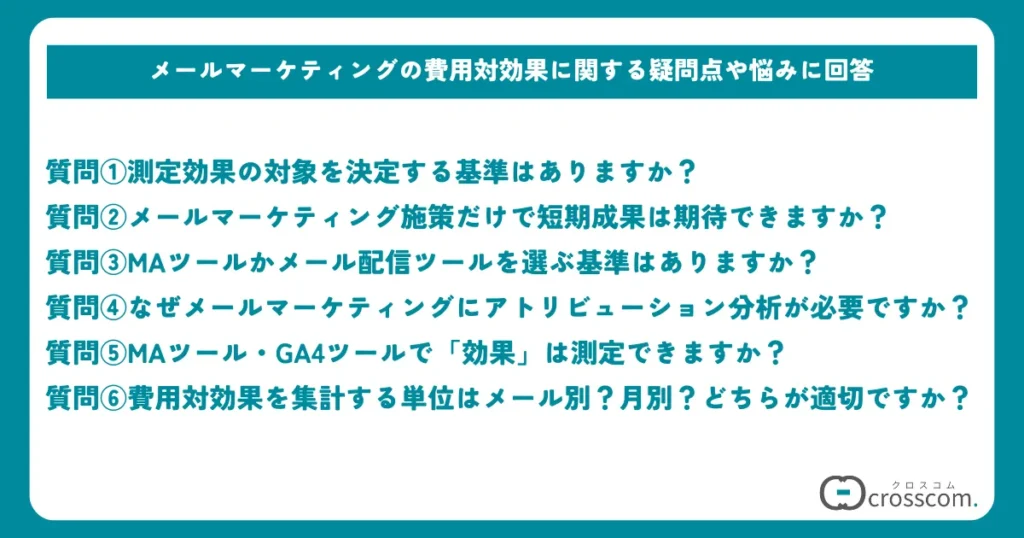
最後に、実務でメールマーケティングの費用対効果に関する疑問や悩みに関する質問にQA形式で回答していきます。
質問①測定効果の対象を決定する基準はありますか?
主軸は「商談・受注・売上」だが、長期のブランド指標は別枠で定点管理すると考えたほうがいいでしょう。費用対効果は意思決定に直結する数値である一方、BtoBではブランド想起や好意度が後年の商談率に効いてくるからです。正しい測定方法がより複雑化するため、商談や成約受注といった直接的な成果のみに焦点を当てるのが妥当でしょう。
質問②メールマーケティング施策だけで短期成果は期待できますか?
ハウスリストの購買意欲の高さと、コンテンツやサービスのオファー設計が整う条件がそろえば、短期成果は期待できるでしょう。関心が高く、購買意欲の高い見込み客は、ターゲットを絞ったメルマガや一連のステップメールに対して、話を聞く即座に行動を起こすことも十分
実際、当社の支援事例でも、外部購入リスト数千件のリードに対してマーケティングメールとサービス紹介メールを織り交ぜて配信し続けた結果、4カ月で商談数が300%、粗利が170%増加しました。
質問③MAツールかメール配信ツールを選ぶ基準はありますか?
組織の規模やフェーズ、社内で取り組んでいる課題やリソースなど、企業1社1社によって選ぶ基準は変わります。
特に持つべき視点は「課題」です。売上・利益を最大化する目的で導入するなら、具体的に取り組んでいる課題の解決を最上位目的として、論点を洗い出してから必要な機能を特定するようにしましょう。そうすると、MAツール・メール配信ツールどちらを選ぶかの基準は自然と決まるでしょう。
質問④なぜメールマーケティングにアトリビューション分析が必要ですか?
メールマーケティング施策だけで商談や受注にはつながらないからです。特にBtoBの購買は複数の接点(記事・ホワイトペーパー・ウェビナー・事例紹介ページなど)を経て成立するため、最後の接点に全功績を与えると、起点や育成の貢献がゼロ扱いになってしまいます。
質問⑤MAツール・GA4ツールで「効果」は測定できますか?
完全には測定できません。GA4はオンライン上のコンバージョンしか計測できないため、商談後の受注数やオフラインでのコンバージョンは計測できないからです。マーケティング部署内では完結できないため、CRMツールと連携しつつ営業組織を巻き込む必要があります。
質問⑥費用対効果を集計する単位はメール別?月別?どちらが適切ですか?
意思決定は月別・キャンペーン別、改善はメール別が基本です。一通のメールは長い購買プロセスの一部であり、単体の数値は揺れが大きいため、意思決定を左右するほどのインパクトがないからです。月次またはキャンペーンレベルのパフォーマンスを見ることで、メール接触があったリード、商談、または収益を、費用と比較しながら費用対効果を算出することができます。
メールマーケティング施策の費用対効果を正しく評価して予算配分を決めましょう
メールマーケティングの費用対効果を正確に算出し、適切に評価することは、限られたマーケティング予算を最大限に活用するための重要なスキルです。特に中小企業のようにリソースが限られている場合は、どんな施策でもこの「費用対効果」を明確にして意思決定することが求められます。
本記事で解説した算出方法を活用することで、単なる開封率やクリック率といった表面的な指標ではなく、事業成果に基づいて施策パフォーマンスを正しく評価できるようになります。
今回は短期的な視点で商談・受注を効果項目としましたが、長期的なブランド構築やプレファレンスといった側面も含めて総合的に評価する「投資対効果」も、継続的に事業を行う上で重要な視点です。
マーケティング部署だけに限らず、顧客体験全体まで対象範囲を広げて算出できるよう、営業部署とも協力しながら費用対効果を高めていきましょう。この記事が、費用対効果の算出に少しでも役立てれば幸いです。
